鈴木竜太氏
神戸大学大学院経営学研究科教授
1999年神戸大学大学院経営学研究科修了(博士<経営学>)。静岡県立大学経営情報学部専任講師を経て、現職。専門分野は経営組織論、組織行動論、経営管理論。著書に『関わりあう職場のマネジメント』(有斐閣、2013年:日経・経済図書文化賞、組織学会高宮賞)、『経営組織論(はじめての経営学)』(東洋経済新報社、2018年)など。

日本企業を取り巻く経営環境の変化に伴い、組織を導くリーダーのあり方も変遷を遂げてきた。経営課題がますます多様化・複雑化するなかで、リーダーシップもさらなる変化が求められている。
不確実性の時代のリーダーが備えるべき資質・能力とは何なのか。組織行動論やリーダーシップ論の分野で先進的な研究に取り組む、神戸大学大学院経営学研究科教授の鈴木竜太氏に聞いた。
リーダーシップとは、集団をまとめ上げ、組織の目標達成に向けて導いていく力のことだ。企業が目指すべき目標や成果は、時代や経営環境の変化によって変わっていく。おのずと、ビジネスで求められるリーダーシップのあり方も変遷を遂げてきた。組織行動論の専門家である鈴木竜太氏によれば、日本経済の過去40年のなかで、リーダーシップをめぐる大きな転換点は2度あったという。
1つ目の転機は1990年代初頭のバブル崩壊の時期だ。
「日本経済が右肩上がりで安定していたそれまでの時代は、計画を着実に実行する指示型リーダーが重視されました。しかし日本経済が本格的な低成長時代を迎えると、変革を推し進めるカリスマ型の強いリーダーシップが求められるようになりました。大規模な組織改革や人員削減なども断行しながら、閉塞感を打破し、新たなビジネスを立ち上げていけるリーダーが期待されたのです」(鈴木氏)
もう1つの転機は2000年ごろになる。グローバル競争の激化、地球環境問題をはじめとする社会課題の複雑化、働く人々の価値観の多様化などに伴い、変化に柔軟に対応しながらチームの創造力を引き出すリーダーが求められた。
「従業員が気持ちよく前向きに働ける環境を整える必要性が高まったこと、新しい取り組みを進めるうえで、現場社員が自発的に考え行動することが重要になったことも背景にあります。従業員=フォロワーを企業活動の中心に据えた支援・共感型のリーダーシップが重視されるようになりました」(鈴木氏)
支援・共感型リーダーシップがカリスマ型リーダーシップに完全に取って代わったわけではなく、現在もこの2つは併存している。それぞれ課題もあり、カリスマ型は力強い変革を進めやすい半面、独裁的な組織運営に陥り、現場を疲弊させてしまうおそれがある。一方の支援・共感型は、社員の能力を発揮させやすい面があるが、一人ひとりの特徴を把握して能動性や自律性を引き出し、適切に制御するのは容易ではない。この方法で成果を導くことに苦戦しているリーダーも少なくないだろう。
どちらが良いとは言い切れない。確かなのは、企業が直面する課題はこれまで以上に複雑化し、目指すべき成果やゴールも1つではないという点だ。現在のリーダーには複数の目標を同時達成することが求められており、リーダーとして極めて高度なスキルと多面的な対応力が必要になる。その意味で、これからのリーダーは特定の職務経験に長けているというだけで担えるものではなくなったと鈴木氏は話す。営業成績の良い社員を営業部門のリーダーにするといったやり方では、チームの成果を上げるのは難しい。
「今後は、“リーダーの専門職化”が進む可能性があります。若いうちからリーダーになるための実践的なトレーニングを受け、必要な資質・能力を身につけたメンバーのなかから、最も適した人財をリーダーにするという流れが主流になるかもしれません(図1参照)」(鈴木氏)
例:営業成績トップの社員が次期リーダーになる

例:複数の目標を同時達成する対応力、メンバーに対する理解力や想像力を学んだ社員がリーダーになる
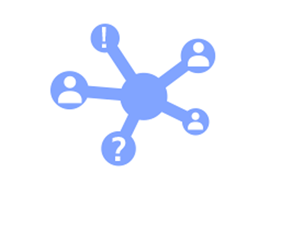
従来は特定の業務スキルが高いメンバーをリーダーとする組織が多かった。社会の多様化・複雑化に対応するには、「人に対する理解力」「想像力」といった、業務スキルではない部分が重要になる
出典:鈴木竜太氏のインタビューをもとに作成
では、これからのリーダーが備えるべき能力とは何か。最も重要かつ基本的な能力は「人に対する理解力」だという。組織としての成果は、突き詰めれば「人」にかかっている。人に対する理解の解像度が高いほど、リーダーシップを発揮する際のアプローチの幅は広がり、対応の質も高くなる。
そして、この「人に対する理解力」を大きく左右するのが「イマジネーション(想像力)」だと鈴木氏は強調する。
「どのように働きかけたらチームメンバーは最も良い行動をしてくれるか」
「Aさんに対し、どうアプローチしたら最も高いモチベーションで動いてくれるか」と、相手の内面を想像しながら働きかけて良い関係を築き、適切な行動に導く能力である。言葉で表すのは簡単だが、身につけるのは容易ではない。最近は価値観の多様化が進み、求められるイマジネーションもより複雑になっている。経験の豊富さで養われるものでもなく、むしろ過去の成功体験が他者理解を妨げるおそれもある。
このような能力を身につける1つのヒントとして鈴木氏が挙げるのが、近年のリーダーシップ教育の分野で用いられる「Knowing,Doing,Being」のフレームワークだ。Knowingとは、人々の考え方や社会のあり方を広く捉える知識、Doingは実践のためのスキルや技能、Beingは「自分はリーダーとしてどうあるべきか」というアイデンティティや内面性を意味する。
「私の印象ですが、これまでの日本のリーダーシップ教育はDoingやスキルセットに偏っている傾向があるように感じます。社会に対する深い知識や自己の内面的な成長を軽視すると、リーダーとしての人間的な土台が弱くなってしまう。広く社会に目を向け、その背景にある人々の多様な価値観への理解を深めたり、あるいは自分が仕事を通じて本当に大事にしたいものは何か、リーダーとして組織をどう導きたいのか、内面性を掘り下げたりする機会を、企業として意識的に増やす必要があるはずです。それが想像力も含む、リーダーとしての本質的な成長につながるのではないでしょうか」(鈴木氏)
ここまで、主に経営層やマネジメント層を想定したリーダーシップについて述べてきたが、経営環境の変化に迅速に対応するため、今後は日本でもアジャイル型やプロジェクト型の柔軟な組織運営の広がりが予想される。そうなれば、リーダーシップは一部の役職者に限らず誰もが日常的に求められる時代になるだろう。その意味で企業には、あらゆる社員の自律性を育む環境の整備が求められる。
自律性を高めるカギは、鈴木氏によれば2つあるという(図2参照)。1つは「余白」。仕事のなかに考える余地を残すことだ。マニュアル化された業務では、自律的な判断や創意工夫は生まれにくい。ホワイトカラーの現場でも、厳密なフォーマットに沿って進める仕事が多い場合は自分で考える力が育たない。仕事を任せる際には、本人の判断や工夫が入り込める余白を設けることが重要だ。
もう1つは「問いかけ」の質。「自由に考えて」と問うても、上司のなかに“正解”があるような雰囲気では、部下も無意識に“正解探し”をしてしまう。相手が本気で考えたくなるような、自律性を刺激する問いの出し方や仕事の与え方が大切になる。
「仕事を差配するリーダーの力量が問われる時代になっています」(鈴木氏)
経営環境の変化に伴い、役職者ではないメンバーでもリーダーシップを発揮する必要のある場面もより増えていくことが予想される。企業には、組織内の自律性を高める仕組みを整えることが求められる
出典:鈴木竜太氏のインタビューをもとに作成

鈴木竜太氏
神戸大学大学院経営学研究科教授
1999年神戸大学大学院経営学研究科修了(博士<経営学>)。静岡県立大学経営情報学部専任講師を経て、現職。専門分野は経営組織論、組織行動論、経営管理論。著書に『関わりあう職場のマネジメント』(有斐閣、2013年:日経・経済図書文化賞、組織学会高宮賞)、『経営組織論(はじめての経営学)』(東洋経済新報社、2018年)など。