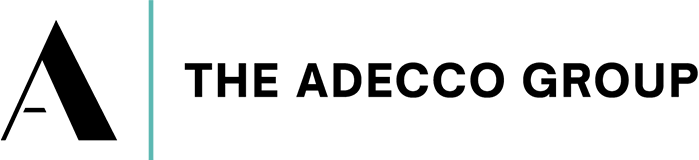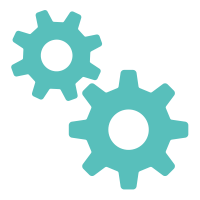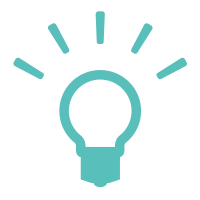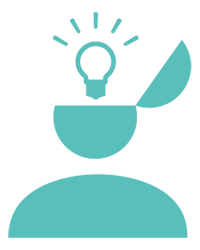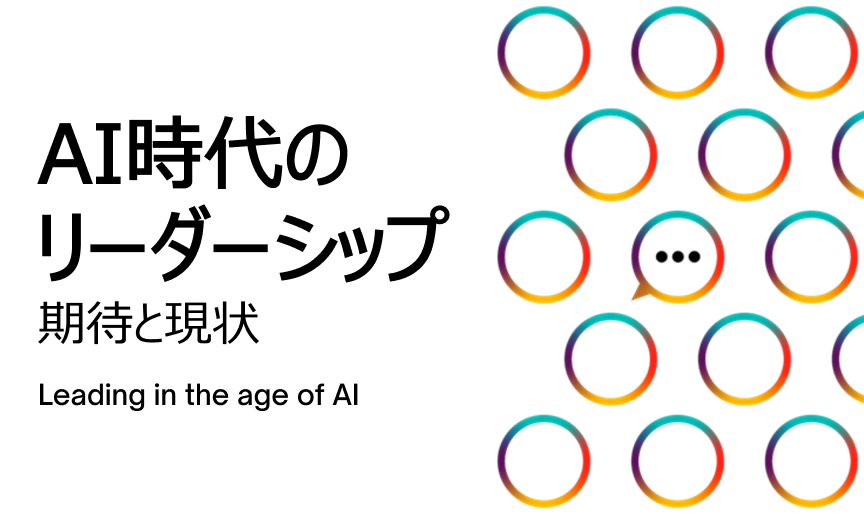ChatGPTが2022年11月に公開されてから2年余りが過ぎた。生成AIはビジネスにおいても生活者の日常生活においても切り離せない存在になり、AI技術が組み込まれた製品も珍しくはなくなっている。だが、AI技術を社内業務で積極的に活用しているかどうかは企業間で温度差がある。
日本企業のAI活用の実態や今後のAIの進化と企業経営の関係について、「人と共生できるAI」の実現を研究する慶應義塾大学教授の栗原聡氏に話を聞いた。
世界の主要国に比べてAIの浸透度が低い日本
ChatGPTの登場以来さまざまな生成AIが登場し、日本の職場でもAI活用が進んでいるといわれる。実際のところどの程度、浸透しているのか。
「会社によって温度差はあるようですが、全体的に見れば日本企業での浸透度は他の先進国に比べて高いとはいえない状況です。Amazonが巨大倉庫の自動化システムを一気に導入したように、巨大な資本力を持つ会社とそうでない会社で差が生まれています。加えて日本企業の場合は、生成AIをどう事業活動に役立てればいいのかわからない、というのが実情だと見ています」と栗原氏は推測する。たとえば顔認証システムのために数万人の画像を学習し終えたAIであれば、具体的な用途や活用シーンも浮かんでくる。だが、生成AIは人類のほぼすべてのデータを学習していて、活用用途はほとんど無限に考えられる。あまりのスケール感の違いに、使い道を確定できない状態なのだという。
「生成AIは、道具の域を超えています。本来、道具とは人間の作業を補助するものですが、生成AIは人間にしかできないと考えられてきたことができてしまう。ここに、従来の道具(ツール)との本質的な違いがあります」
人間にしかできない作業をしてくれる道具を手に入れたのは、人類にとって初めてのことだ。今、起きているAIにより生じている格差は、未知なるものに対するアプローチの違いだと栗原氏は見ている。
「アメリカ人は未知のものに対して、何ができるか知ろうと徹底的にトライ・アンド・エラーを繰り返します。一方で日本は失敗に対する許容量が少なく、一定の知見や見通しができない間は静観する傾向にあります。そうした国民性の違いが、浸透度に差を生んでいるように見えます」
格差に関するもう一つのキーポイントは中間管理職だという。今このポジションを担う層は、AIのない時代にたたき上げでキャリアを築いてきた世代といえる。AIに頼らずとも十分成果は出せる、AIに頼るのは不誠実なやり方だと考えるマインドも根強い。
「人の価値観はそう簡単には変わりません。仕事に誠実な日本企業が真にAI活用に向き合えるまで、世代交代が起きる10年以上のスパンが必要かもしれないと思っています」
手をこまねいていると、さらに水を開けられてしまうと不安になるが、栗原氏はその心配はないという。
「時が来れば、一気に盛り返せる潜在力が日本にはあります。AIもタイミングが来ればキャッチアップできるに違いありません。むしろ企業にとっては、AIの本質を理解しないまま、経営層が闇雲に号令をかける方が危ういと思います」
「歯車」と「モーター」、仕事は大きく2つに分かれる
データ上には表れていないものの、日本の職場でも人とAIの転換が静かに進んでいると栗原氏は見ている。
「率直にいえば、企業内ではすでにAIの導入コストと人件費とを比較しています。AIの方が低コストならAIを導入し、人の方が利益を出せるなら人のまま。転換は徐々に進んでおり、いずれ人とAIは逆転するでしょう。その過程で仕事は『歯車』型と『モーター』型の2つに分けられます(図1参照)。『歯車』は生成AIに転換できる仕事。『モーター』は状況に合わせて工夫したり、異なる分野の人やモノをつないだり、チームをまとめる仕事です。今後はモーター型の人財をどれだけ獲得できるかが、企業の競争力を分けることになります」
図1「歯車型」の仕事と「モーター型」の仕事
【歯車型】
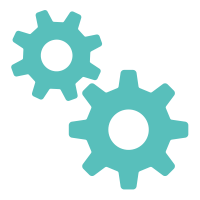
【モーター型】
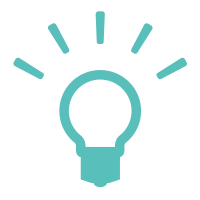
生成AIを使いこなす
自社業務にイノベーションを起こす
これからの仕事は「歯車型」の仕事と「モーター型」の仕事に分かれる。
後者を担う人財が必要だ。
モーター型人財には、生成AIを使いこなす能力が求められる。しかしそれは、書類作成といった業務効率化に活用する能力のことではない。
「AIを使いこなす能力とは、自社に役立つイノベーションに活用できる力のことです。たとえば私は2023年にAIで『ブラック・ジャック』の新作漫画をつくるプロジェクト『TEZUKA2023』を行いました。その現場で人間に求められたのは、AIが提案するストーリーの面白さを理解する力や、そのストーリーが手塚作品の世界観と合致するかどうかを判断する力、そして他の要素と組み合わせてより深みを増すアイデアを提案する力でした」
基本的にAIは使う人の能力以上の結果は出せないと、栗原氏はいう。AIが発達すればするほど、それに見合う優秀なモーター型人財が必要になる。
「モーター型人財とは、自らの関心と行動力でトライ・アンド・エラーを繰り返し、幅広い知識と高度な理解力、判断力を身につけていく人のことです。そうした優秀な人財を見分けるには、相応の時間がかかります。日本企業も、新卒一括採用から時期を問わず希望者が実力をアピールする米国企業型の採用スタイルに変わっていくように思います」
「予測できない世界」に向け企業が持つべきはAIではなく人を起点とした広い視野
モーター型人財の登場が期待される一方、栗原氏が懸念するのは、若年層のスマホとの向き合い方だという。
「スマホでインターネット検索すればどんなことでも即時に答えが出てきます。そのため自分の頭で考えない若年層が増え、思考力の低下傾向が見られます。スマホの指示に忠実に従う歯車人財が増えているともいえます。AIネイティブの彼らにこそ、ぜひAIを使いこなすモーター型の力を身につけてもらいたい」
道具を使いこなすという意味ではリスキリングにも注意が必要だという。リスキリング=DX人財の養成と考えるのは方向性が異なると指摘する。
「DX人財が一定数必要なのは確かですが、生成AIは『エージェント』という自律型のAIへ進化しています。人間が指示しなくても、AI自身が判断して動く。要は『ドラえもん化』しています。のび太はドラえもんの知能構造は理解していませんが、うまくつき合っています。同様に、エージェントを使いこなすにはAIプログラミングの知識よりも、AIで何がしたいのかという目的意識が問われます。それがないとAIに使われる歯車になってしまうのです(図2参照)」
図2AIを使いこなす「モーター型」人財像
自らの関心と行動力でトライ・アンド・エラーを繰り返す
幅広い知識と高度な理解力、判断力を身につけている
異なる分野の人やモノをつないだり、チームをまとめたりする
生成AIは「エージェント」という自律型のAIへと進化している。AIに使われる歯車にならないためには、AIプログラミングの知識よりも、「AIで何をするか」という目的意識が重要になる。
まもなくAIが人間の知能を超える「シンギュラリティ」も起こるといわれている。栗原氏はこれからのAIの発展をどのように見ているのだろうか。
「人工知能の構想は1950年代に生まれ、ディープラーニングの手法も60年代に考えられたものですから、ここまでは“起こるべくして起きた変化”でした。しかし、ここから10年後は予想もつきません」
いずれ、稼ぐ仕事はAIが担うようになると栗原氏は予測する。それによってベーシック・インカムが整備されたとき、人間の職業観は「どうやって食べていくか」ではなく「何がしたいのか」に価値が置き換わるという。
「企業にとっては当面、AIをいかに利益につなげるかが関心事だと思いますが、もっと視野を広く、人間はAIを使って何を成し遂げられるのかという視点が重要になるでしょう」
Profile
栗原 聡氏
慶應義塾大学 理工学部 教授
人工知能学会 会長
慶應義塾大学共生知能創発社会研究センター
センター長
慶應義塾大学大学院理工学研究科修了。博士(工学)。NTT基礎研究所、大阪大学、電気通信大学を経て、2018年より現職。マルチエージェント、複雑ネットワーク科学、計算社会科学などの研究に従事。科学技術振興機構(JST)さきがけ「社会変革基盤」領域統括などを歴任。著書に『AIにはできない人工知能研究者が正しく伝える限界と可能性』(角川新書)など多数。